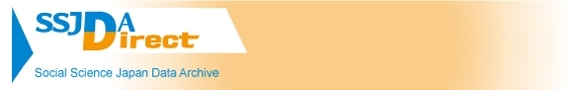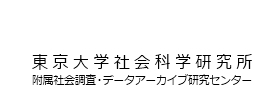| 概要 | ||
| 調査番号 | 1654 | |
| 調査名 | 貯蓄と消費に関する世論調査, 1992 | |
| 寄託者 | 金融経済教育推進機構 (寄託時:金融広報中央委員会) | |
| 利用申込先・承認手続き |
利用方法の詳細はこちら
SSJDAが利用申請を承認したときに利用できる |
|
| 教育目的(授業など)の利用 | 教育(授業・卒論等)も可 | |
|
利用期限 |
一年間 | |
| データ提供方法 | ダウンロード | |
| オンライン集計システムSSJDA Data Analysis | 利用不可 | |
| 引用・謝辞の例 |
二次分析の結果を発表する際には,個票データについて以下の文を付することにより,個票データの出典を明記してください。 二次分析にあたり,東京大学社会科学研究所附属社会調査データアーカイブ研究センターSSJデータアーカイブから 「貯蓄と消費に関する世論調査, 1992」 (金融経済教育推進機構) の個票データの提供を受けました。 https://doi.org/10.34500/SSJDA.1654 ※例えばシリーズで複数調査をご利用になられた場合は調査名の箇所にシリーズ名を記載するなど,状況に応じてご修正いただけると幸いです。ご不明点等ございましたら ssjda@iss.u-tokyo.ac.jp までお問い合わせください。 |
|
| 調査の概要 |
本調査は,貯蓄や借入金の実態,生活設計や家計管理の状況などを把握して貯蓄運動に役立てることを目的として,全国の普通世帯(世帯員2名以上の世帯)を対象に実施したものである。 主に,貯蓄,消費等,生活設計などが調査項目に含まれる。 |
|
| データタイプ(量的調査/質的調査/官庁統計) | 量的調査: ミクロデータ | |
| 調査対象 | 世帯員2名以上の普通世帯 | |
| 調査対象の単位 | 世帯 | |
| サンプルサイズ | 4,138世帯(回収率 69.0%) | |
| 調査時点 |
1992-06-24 ~ 1992-07-03 1992年6月24日~7月3日 |
|
| 対象時期 |
1992 ~ 1992 |
|
| 調査地域 | 日本 全国 | |
| 標本抽出 | 確率: 層別抽出: 比例割当法 確率: 多段抽出 層化2段無作為抽出法により全国から400地点を選び,各調査地点から無作為に15世帯を選ぶことによって計6,000の調査対象者を抽出。 | |
| 調査方法 | 自記式調査票:紙 | |
| 調査実施者 |
|
|
| DOI | https://doi.org/10.34500/SSJDA.1654 | |
| 委託者(経費) |
|
|
| 寄託時の関連報告書・関連論文 | 貯蓄広報中央委員会,1992,『貯蓄と消費に関する世論調査 平成4年』貯蓄広報中央委員会,1992年11月 | |
| SSJDAデータ貸出による二次成果物 | 二次成果物一覧はこちら | |
| 調査票・コードブック・集計表など | 【 調査票 】 | |
| 主要調査事項 |
(1)貯蓄 年間手取り収入(臨時収入を含む)からの貯蓄有無,年間手取り収入からの貯蓄割合(%),ボーナス・臨時収入等からの貯蓄有無,ボーナス・臨時収入からの貯蓄割合(%),現在の貯蓄保有状況,貯蓄商品別残高,今後1年間に貯蓄を増やしていく場合の商品別構成比,貯蓄商品の選択基準,家計の貯蓄残高の評価,貯蓄残高の1年前との増減比較,貯蓄残高が増加した理由,貯蓄残高が減少した理由,貯蓄の目的,貯蓄目標残高,貯蓄目標達成予定時期,小口MMCの預入状況,小口MMC残高,自由金利定期預貯金の預入状況,自由金利定期預貯金に預入した理由,自由金利定期預貯金残高,自由金利定期預貯金に預入しない理由,貯蓄預貯金の預入状況、貯蓄預貯金に預入する理由,貯蓄預貯金残高,金融機関の選択理由,金融機関のサービスについての不満・改善点,金融自由化の発展に関する考え (2)消費等 過去1年間の収入・支出内訳,前年と比較した過去1年間の消費支出,消費支出を増やした項目,消費支出を減らした項目,家計の支出の1年後の増減予想,消費支出を増やす予定の項目,消費支出を減らす予定の項目,過去消費支出で重視した・重視する項目(過去1年間・今後1年間),借入金の有無,現在の借入金残高,借入先内訳,借入目的,クレジットカードの利用状況(クレジットカードの保有枚数,1年間の利用回数・1年間の利用金額),クレジットカードを積極的に利用する・利用しない理由,プリペイドカードの利用状況(購入枚数,購入金額,使用金額),家計支出の資金決済手段(現金・クレジットカード,プリペイドカード,口座振替),資金決済額全体のうち現金決済の割合,月平均手持ち現金残高 (3)生活設計 経済的な豊かさの実感,経済的な豊かさを実感する条件,現在・1年後の暮らし向きへの考え,消費生活・消費スタイルに関する考え,生活意識に関する考え,生活設計の有無・スパン,家計簿の記録の有無,現在の住居状況,住宅取得予定時の世帯主の年齢,高水準のマイホーム購入価格への対応方法,住宅取得必要資金(うち自己資金,借入金),老後の暮らしについての経済面の考え(60歳未満),心配していない理由(60歳未満),心配である理由(60歳未満),暮らし向きについての考え(60歳以上),生活費の収入源(60歳以上),豊かな老後の実現に必要なこと(60歳以上),こどものこづかい額 (4)フェイス項目 世帯人数,世帯主年齢,世帯主の職業,家族の就業状況,地域,都市規模 |
|
| 公開年月日 | 2025/02/07 | |
| CESSDAトピック |
詳細はこちら 所得、財産、投資・貯蓄 |
|
| SSJDAオリジナルトピック | 経済・産業・経営 | |
| バージョン | 1 : 2025-02-07 | |
| 特記事項 |
|